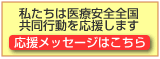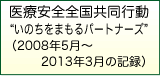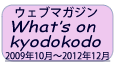被災者支援のための緊急提案
3月11日の東日本大震災の発生から1か月が過ぎ、復興をめざす動きが始まっている。
しかし被災者の保健・介護・医療はまだ救援期にあり、今この時の支援が求められている。
死者・行方不明者は2万8千人を数え、10万人を超える方々が今も避難所生活を強いられている。 これほどの規模と広がりを持つ災害に、自らが深刻な被災者である現地自治体のキャパシティで対処することは不可能である。今必要なことは、被災自治体と支援自治体とのペアリングによるシステムまるごとのバックアップ体制と、援助が必要なすべての被災者により添える統率された人海的支援である。
災害による可避死(避けられる死)は、津波・地震等災害事象自体による傷病、劣悪な避難生活環境と、地域保健医療システムの破壊に起因する。阪神淡路大震災後に準備されたDMAT(災害派遣医療チーム)と赤十字・自衛隊ほかの迅速な展開で医療の救出救助活動は一定の成果を上げた。しかし、発生直後に生死が分かれる津波災害では、災害の後からリスクが蓄積されており、可避死が顕在化するのはこれからである。
1ヶ月を経過してなお炭水化物中心の低カロリーの避難食で、糖尿病や高血圧、腎臓病の方々もひとしく避難食を続けており、病状の悪化が懸念されている。治療や検査の中断に加え、水が出ないトイレや密集した部屋は感染症拡大のリスクを高め、重油の混じった塵埃、硬い床の寝床に着たきりの毛布、段ボールの仕切りだけのホームレス生活、介助者を失った高齢者や障害者など、避難者のリスクは日々蓄積されつつある。
1.被災自治体と支援自治体のペアリングによる組織的支援-人とシステムの提供を-
災害はシステムを破壊する。病院や診療所がなくなり、保健活動や医療や介護に従事する人々が被災し、システムを支える様々な機能が停止または消失した。
公衆衛生・予防保健・診療サービスを提供する地域保健医療システムは、母子保健、栄養、環境衛生、感染対策、高齢者や障害者の援護、予防検診・予防接種などの保健福祉活動から、訪問看護、救急搬送・夜間診療、プライマリーケアから高度専門医療までの診療態勢、診療に不可欠な輸血や検査のシステム、医薬品のサプライ、機器の保守管理、など、さまざまなサブ・システムで構成されている。システムを支えているのは、医師と施設だけではない。さまざまなしくみや、ルールや、ノウハウや、手順や書式、移動手段や通信手段、情報ネットワークなど、多数の基本要素がたがいに繋がってシステムが支えられているが、これらがまるごと被災した。これらを部品ごとに切り貼りする形の支援(業務や活動ごとに、それぞれ異なるシステムから異なるしくみやノウハウを持ち込む)ではシステムとして機能することが困難である。システムの支援は、必要に応じて補完、補佐、代替が可能なシステムのパッケージでバックアップする必要がある。
今回の震災では被災者救護と復旧を担うべき市町村の行政システムが同様に破壊された。 市・町の庁舎・支所も、病院も、保健所も破壊され、職員や医療者も行方不明となり、あるいは住む家を失って避難所に寝泊まりしながら、発災以来休む間もなく文字通り献身的に被災者の支援に従事してきた。県職員も同様である。心のケア専門家チームの調査で最も心のケアを必要としていたのは市の職員たちだった。
この災害は自ら被災した自治体が対処できるものではない。今求められているのは、被災した市・町ごとに、これを支援する自治体(特定県とその市・町)をペアリングすることによって、損傷したシステム(行政機能を含む地域保健医療システム)を現存するシステムで補完しバックアップすることである。
2.被災市町がすぐに自由に使える緊急災対基金の支援を―
インフラの修復が少し進み、ようやく本来の業務や活動に従事できるようになり、アセスメント調査やサーベイランス、要援護者の把握、衛生管理や栄養対策、心のケア、感染対策、など遅れていた取り組みが急がれているところである。しかしながら、多くの避難所はまだ電気も水もなく、避難所や在宅被災者へのアプローチが滞っている。事前に計画されていた避難所の生活物資や避難食、医薬品の配備は比較的速やかに行われたが、通信手段や移動手段の確保、栄養管理食ほか各種業務の外部委託、必要機材・物品の調達など、具体的な個別ニーズに対応できる財源がないために緊急の調達が困難な状態にある。
市町の裁量で使える基金や予算がないために、現場は今あるものでやらざるを得ないとあきらめており、そのことが種々の対応に遅れをもたらしている。
復興への準備もさることながら、災害によって多くの資源が失われた今この時にこそ、現場である市町が自ら裁量してすぐに使える緊急災対基金を創設する必要がある。
3.協調的な支援と、すべての被災者、避難者により添う派遣を-
災害から1か月が過ぎて復興が主な話題になってきたが、被災した人々のいのちと生活に直結する保健・介護・医療は、いまなお救援期にある。
災害直後の緊急期は外部支援が期待できないため、災対関係者は、「被災者のためにやれることをできるだけやる」ことに全力を注いだ。アクセスができて現場の情報が得られるようになり支援が届くようになった救援期は、「被災者のためにやらなければいけないことをやる」時であり、そのためには、「やるべきことをやれるようにする」ことが重要である。
人的・物的・時間的資源が圧倒的に不足する現場の一義的な役割はニーズを把握し外部資源を効果的に投入することである。しかしながら、緊急期から災対に従事してきた現場の心理は「やれることをできる限りやる」にセットされたままで、外部支援にはあまり期待していないため、支援ニーズや要請が発信されにくい状態にある。能動的で積極的な支援が必要である。
大きな制約の下でも現場の懸命の努力によって徐々に対応がなされつつあるが、一方で避難所や地域による格差が目立ってきた。救援期における支援は、迅速で効果的で協調的であることが何よりも重要で、やりたいことよりも、現場が必要としていることに柔軟かつ迅速に対応することに意を用いるべきである。外部からの支援は善意に反して現地の資源-とりわけ現地カウンターパートの人材と時間-を奪い合うか、負担をかける結果に陥りやすい。 支援に関わる機関や団体は、システムの再建も見据えながら、当面する問題を解決するための目標と方法を共有し、役割を分担し、相互に補完しあいながら、貴重な資源を効果的に投入していただきたい。外部支援の受入れには調整のしくみと要員が必要で、この点でも、ペアリングのパートナーとなる自治体の業務支援が望まれる。
10万人を超える被災者が、いまなお劣悪な環境でマス(集団)の一員としての避難生活を強いられている。被災者の一人一人が、それぞれの被災体験を持ち、新たな人生設計を余儀なくされている。とりわけ、高齢者や病気・障害を持つ方々は、これまでの支えを失い、適切な介護や看護を受けられないまま日が過ぎている。被災者を援助している職員や地域の人々にも休息が必要である。今後、避難所の集約や移転が進むが、これらが円滑かつ適切に行えるためにも「何でもやる」ボランティアが必要である。今各地で被災者の調査が進められているが、調査する人の数も移動手段も足りない。例えば、まとまった数の車と運転手を提供するボランティア団体があるだけでも多くのことが促進される。
被災者と被災地域がこれだけの数である。市町・県の職員と被災地住民だけでは、また統率されない散発的なボランティアでは、多くのことが遅きに失する。今この救援期にこそ、支援者を計画的、集中的に投入して、被災した方々が1日も早く健康と尊厳を回復できるよう、被災者、避難者により添える支援を呼びかけたい。
これは「東北の不運な町の災害」ではない。これは日本の災害であり、「日本」が問われている災害である。日本人の一人一人に、いま自分にできることを考えてみてほしい。
上原鳴夫
東北大学大学院医学系研究科教授
宮城県災害保健医療アドバイザー
2011年4月15日