日本医師会会長 松本 吉郎
日本歯科医師会会長 高橋 英登
日本薬剤師会会長 岩月 進
日本臨床工学技士会理事長 本間 崇
医療の質・安全学会理事長 水本 一弘
(2024年9月現在)
医療安全全国共同行動の活動に寄せて
■公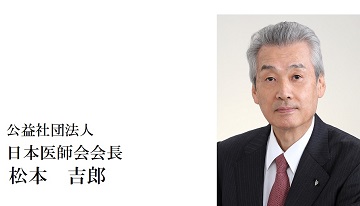 益社団法人日本医師会は、2008(平成20)年の医療安全全国共同行動 “いのちをまもるパートナーズ” 発足当初より、2013(平成25)年の法人設立を経て現在に至るまで、わが国の医療安全文化の醸成に向けて、設立呼びかけ団体として諸団体の皆さまと共に力を合わせて参りました。
益社団法人日本医師会は、2008(平成20)年の医療安全全国共同行動 “いのちをまもるパートナーズ” 発足当初より、2013(平成25)年の法人設立を経て現在に至るまで、わが国の医療安全文化の醸成に向けて、設立呼びかけ団体として諸団体の皆さまと共に力を合わせて参りました。
■患者さんを中心とした現代の医療は、多くの医療関係職種、事務職員、地域の関係機関などが協力し合い成り立っていることは申すまでもありません。こうした医療の質を今以上に高め、患者さんにとって安全で安心な医療を提供し続けていくためには、医療に携わるあらゆる職種の人びとが互いに知恵を出し合い、忌憚のない議論を重ねることが効果的です。その点で、医療安全全国共同行動がこれまで取り組んで来られた活動は、わが国の医療安全に留まらず、医療提供のあり方そのものに対しても、多大なる影響を及ぼしてきたものと言って過言ではありません。
■日本医師会では、1997(平成9)年より会内に医療安全対策委員会を設置し、医療事故の防止と患者安全に向けた取り組みについて議論しています。特に近年は、医療事故調査制度における、各医療施設の院内調査を適切に実施するための基本的な手法や考え方を重点的に検討しています。医療事故の原因究明と再発防止を目的とする院内調査では、何が起き、それはなぜ引き起こされたのかを医学的に明らかにすることが重要となります。そのためには、医療提供に携わったさまざまな職種や立場にある職員から、些細なことも捨象せずに現場の情報を聴き取ることが重要となります。実際にこのような考え方にもとづいて院内調査を実施した医療施設では、職種の垣根を越えて多くの職員が協力し合う経験を共有したことによって、その後の医療提供全般において院内の団結が高まったという副次的効果も得られたとのことです。
■医療に携わるすべての職種が、患者の安全という共通の目標に向かって歩み続ける医療安全全国共同行動の取り組みは、これからの医療界全体が進むべき方向性を明らかに示しているものと確信いたします。(2023年6月)
より高度な医療安全の実現に向けて
■医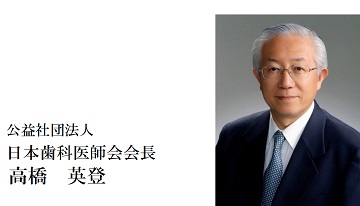 療安全全国共同行動におきましては、設立当初より医療従事者やその専門職能団体、学会等の様々な組織が連携して、一丸となって医療安全対策の実施に取り組んでまいりました。また、患者・市民の皆さんとのパートナーシップを通じて、人々が安心してかかることができる安全な医療を実現することを目指してきました。
療安全全国共同行動におきましては、設立当初より医療従事者やその専門職能団体、学会等の様々な組織が連携して、一丸となって医療安全対策の実施に取り組んでまいりました。また、患者・市民の皆さんとのパートナーシップを通じて、人々が安心してかかることができる安全な医療を実現することを目指してきました。
■日本歯科医師会は、2013(平成25)年以降、医療安全全国共同行動の診療所部会に参画し、診療所における医療安全対策の議論に関わってまいりました。また、日本歯科医師会においては、会内に歯科医療安全対策委員会を設置し、歯科における医療安全対策や院内感染対策、医療事故防止対策等について検討しております。さらに、医療安全研修会や医療事故調査制度研修会等を開催するなどして、都道府県歯科医師会や歯科医療関係者等とともに歯科医療安全対策の推進に力を合わせて取り組んでおります。
■近年、我が国は超高齢社会を迎え、国民の健康に対する意識はますます高まりつつあります。誰もが継続して健康を享受することができる社会の実現のためには、地域包括ケアシステムの構築や医科歯科連携を始めとした多職種連携が不可欠です。我々も他の職種の医療関係者の皆様とも連携して、より高度な医療安全を実現したいと存じます。
■日本歯科医師会は、医療安全全国共同行動の「日本の医療を支える全国の医療機関、医療従事者、医療団体が、職種や専門分野を超えて連携、協力し、患者さんの安全を守り、患者さんと医療者が安心して治療に専念できる医療環境づくりを促進する」という目的に全面的に賛同するとともに、これからもその活動に協力してまいります。(2023年7月)
医療安全全国共同行動に寄せて
 ■医療安全全国共同行動の設立において、医療を担う人々と医療機関、医療を支えるさまざまな団体・学会・行政・地域社会は、立場や職種の壁を超え、一致協力して有害事象の低減と医療事故の防止に総力をあげて取り組むべきとの考えのもと、互いに協力しながら医療の質・安全の確保と向上をめざすといった活動に対し、日本薬剤師会も賛同し「医療安全全国共同行動」の呼びかけ団体として参加してまいりました。
■医療安全全国共同行動の設立において、医療を担う人々と医療機関、医療を支えるさまざまな団体・学会・行政・地域社会は、立場や職種の壁を超え、一致協力して有害事象の低減と医療事故の防止に総力をあげて取り組むべきとの考えのもと、互いに協力しながら医療の質・安全の確保と向上をめざすといった活動に対し、日本薬剤師会も賛同し「医療安全全国共同行動」の呼びかけ団体として参加してまいりました。
■日本薬剤師会におきましては、医療機関に勤務する薬剤師の医療安全に関する行動と同様に、地域における医療提供体制の中で、医薬品や医療・衛生材料を提供する薬局の医療安全管理のための「指針」や「手順書」を作成し、医薬品の適正使用を通じた医療安全の確保を目指しその推進に努めております。そのためには、調剤事故を未然に防止するための情報を収集・分析し、それらを共有し、薬局・医療機関での具体的な対策に繋げていくことが有効であると考え、その活用を図っているところであります。
■昨今、医薬品の供給体制が話題に上がることも多いと思います。医療用医薬品のみならず、一般用医薬品においても、薬剤師が責任をもって対応しなければならないのは、皆様もご理解のあるところだと存じます。医薬品の供給と申しましても、ただ渡すだけといった単純なものではありません。地域住民の医薬品使用の安全性確保には、薬剤師の対面による情報提供が必須であると確信しておりますが、例えば一般用医薬品のインターネット販売等に代表されるように、ともすれば医療を単なるビジネスと捉え、安全よりも経済性を優先する傾向が懸念されるところです。また医療DXも進み、オンライン診療やオンライン服薬指導といった直接の対面による診療・服薬指導でなくてもよい環境が出てきています。もちろん、オンライン診療が不適切な事例に関しては利用できないこととなっておりますが、これは直接の対面診療を補完するための方法であり、安全性よりも利便性が優先されるべきものではないと考えております。
■日本薬剤師会としましても、「医療安全全国共同行動“いのちをまもるパートナーズ”」を通じて、患者さんや地域住民と医療者がともに安心して治療に専念できる医療環境づくりを促進することが必要不可欠だと考えており、これからもその取り組みに協力してまいる所存です。(2024年8月)
医療安全全国共同行動への期待と当会の抱負
■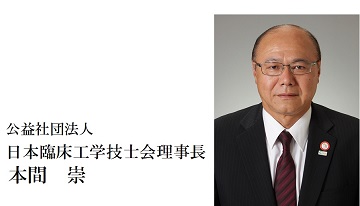 公益社団法人日本臨床工学技士会は、1990年2月に任意団体として設立して以来、各種の生命維持管理装置の操作と安全管理を担う専門職の団体として、医療機器に支えられた高度先進医療を安心して受けられる体制づくりと医療資源の有効活用に日夜努力を重ねています。その社会的使命の達成に向け、2002年3月14日に「社団法人」として厚生労働省から認可を受け、その後、約10年の事業活動の成果を認められ、2012年4月1日に「公益社団法人」として内閣府から認可を受けました。2007年の第5次医療法改正により国民に良質な医療を提供するという目的で、共同行動で取り上げているシリンジポンプ、輸液ポンプ、人工呼吸器はもとより、医療機関で使用する医療機器の安全管理における基本となる運用事項が法律で規定されました。その主な事項は(1)医療機器安全管理責任者の設置、(2)医療機器の保守点検計画の策定と適切な実施、(3)従事者に対する安全使用のための研修の実施、(4)安全使用のために必要となる情報収集、医療機器の安全確保を目的とした改善のための方策の実施、とされています。
公益社団法人日本臨床工学技士会は、1990年2月に任意団体として設立して以来、各種の生命維持管理装置の操作と安全管理を担う専門職の団体として、医療機器に支えられた高度先進医療を安心して受けられる体制づくりと医療資源の有効活用に日夜努力を重ねています。その社会的使命の達成に向け、2002年3月14日に「社団法人」として厚生労働省から認可を受け、その後、約10年の事業活動の成果を認められ、2012年4月1日に「公益社団法人」として内閣府から認可を受けました。2007年の第5次医療法改正により国民に良質な医療を提供するという目的で、共同行動で取り上げているシリンジポンプ、輸液ポンプ、人工呼吸器はもとより、医療機関で使用する医療機器の安全管理における基本となる運用事項が法律で規定されました。その主な事項は(1)医療機器安全管理責任者の設置、(2)医療機器の保守点検計画の策定と適切な実施、(3)従事者に対する安全使用のための研修の実施、(4)安全使用のために必要となる情報収集、医療機器の安全確保を目的とした改善のための方策の実施、とされています。
医療安全全国共同行動への参画と期待
■当会は、医療機器の安全管理を推進するために、2008年5月の医療安全全国共同行動のキックオフ・フォーラムに参画し、行動目標5の技術支援部会メンバーとして関連学会並びに医療機関の皆様とともに輸液ポンプ、シリンジポンプ、人工呼吸器の安全管理の推奨対策を推進してきました。共同行動のホームページでは、医療機器に係る医療事故の発生要因に対する関連学会・団体や行政から示されたマニュアルやガイドラインを基に作成した行動目標達成のための推奨対策とハウツーガイドやツールボックスを掲載しております。また、2007年の医療機器安全管理に関する法律施行の運用事項について「医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施に関する指針」を策定し、この指針を基に作成した「輸液ポンプ・人工呼吸器の日常点検・定期点検実施マニュアル」を共同行動ホームページに掲載しています。法律施行から11年を経て現在も、臨床工学技士が在籍しない多くの施設においては、医療機器に関する教育や適切な使用・保守管理を行うことが難しい現状も散見され、また、医療機器に関連する感染、薬剤も含めた総合的見地に立った医療安全を推進するために、この指針と共に、新たに「医療機器安全管理指針」、「医療機器安全管理指針Ⅱ(研修)」、「医療機器を介した感染予防のための指針」、「医薬品等の調整使用管理指針」、「医療ガス及び電波利用に関する指針」などの指針を刊行し、同時にホームページへの公開を行い広く医療安全への活用を図っております。これら指針についても共同行動の安全対策に活かしていきたいと考えております。ご活用いただければと思います。
■「一般社団法人医療安全全国共同行動」が新たなステージへ向かうにあたり、今後も当会の医療安全対策事業として、職種や立場の壁を超えて、医療を担う病院や診療所とそれを支える団体・学会・行政・地域社会が一致協力して医療事故防止に取り組む「医療安全全国共同行動」の趣旨に賛同し、社員団体として共同行動を支えてまいります。また、私たちの使命である医療機器の安全対策をより力強く推進するため関連団体の皆様並びに全国の臨床工学技士会と一致協力し、より多くの医療機関に対し共同行動への参加を呼びかけてまいります。(2018年3月)
医療安全全国共同行動と共に
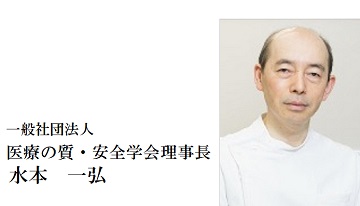 ■一般社団法人医療の質・安全学会は、2005年、初代理事長の故髙久史麿先生を中心に設立されました。多職種、多領域の会員構成の下、医療の質・安全の向上に資する科学的、実践的な研究推進と国内外の研究成果の交流・普及促進を通じて、患者本位の質と安全を提供する新しい医療システムのあり方の実現を目的に掲げている学術団体で、会員数は3000名を超えるまでになっております。
■一般社団法人医療の質・安全学会は、2005年、初代理事長の故髙久史麿先生を中心に設立されました。多職種、多領域の会員構成の下、医療の質・安全の向上に資する科学的、実践的な研究推進と国内外の研究成果の交流・普及促進を通じて、患者本位の質と安全を提供する新しい医療システムのあり方の実現を目的に掲げている学術団体で、会員数は3000名を超えるまでになっております。
■医療安全全国共同行動“いのちをまもるパートナーズ”は、2008年、医療者、医療機関が所属する6つの諸団体と本会との呼びかけで設立されました。その目的は、定款に「日本の医療を支える全国の医療機関、医療従事者、医療団体が、職種や専門分野を越えて連携、協力し、患者さんの安全を守り、患者さんと医療者が安心して治療に専念できる医療環境づくりを促進すること」と記されています。
■医療安全全国共同行動と本会とは、その目的に「患者」と「安全」との共通ワードを有しており、同じベクトルを持って、互いに連携、協働しながら、その活動を継続、発展させてきました。2024年4月には、医師に対する時間外労働上限規制、いわゆる医師の働き方改革の適用が始まります。患者安全のレベルを損なうことなく質の高い医療を提供し、さらに、そのレベルを継続的に向上させていくためには、患者さんやご家族をも含めた多職種協働、タスクシェアが大前提となります。医療安全全国共同行動と本会は、いずれも設立当初より、多職種、多領域の集合体としてタスクシェアを前提に活動しており、時代がようやく追いついてきたと見ることも出来ます。今後、本会は、諸団体とともに医療安全全国共同行動との連携、協働をより強固なものとしていく所存です。医療安全全国共同行動のさらなる発展を祈念いたします。(2023年8月)

